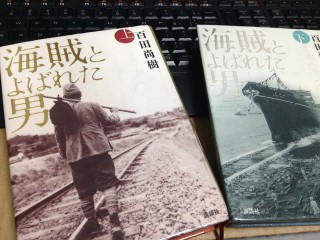
海賊とよばれた男
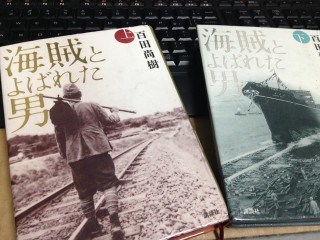 「海賊とよばれた男」(百田 尚樹)を読みました。
「海賊とよばれた男」(百田 尚樹)を読みました。
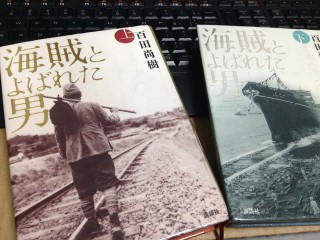
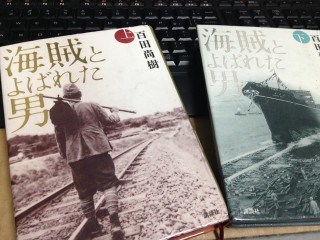 「海賊とよばれた男」(百田 尚樹)を読みました。
「海賊とよばれた男」(百田 尚樹)を読みました。

サッカー日本代表監督の岡田武史氏の公演より(早稲田大学の特別講演)

生き方が痛快。こんな人の元で働いてみたいと思う。
小我にとらわれず、社員や国民、日本国または他国に対しても正しくあろうという姿勢
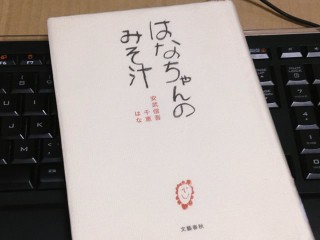
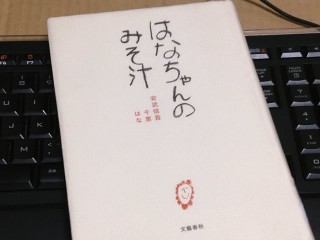 書店で平積みされていた本をなにげなく手にとったのがきっかけで読みました。
書店で平積みされていた本をなにげなく手にとったのがきっかけで読みました。
前書きとして掲載されていた、小学生のはなちゃんが天国のお母さんに向けた手紙から泣けます。

(食べものを選ぶ基準は)命が喜ぶ食べ物であるかどうか。ただ、命が喜ぶ食べ物ほど値段は安くない。

同僚からから教えてもらい、調べたら本を出していたので読んでみようと思った。17歳で世界一、その後プロ・ゲーマーとして地位も名声も手に入れたが、ここまで過程は順風満帆ではなかった。
ゲームは遊びじゃない、自分を向上するための手段、ゲームばかりの後ろめたさや劣等感を抱え、それでもゲームでプロになったまでの経験や考え方。

同僚から紹介された本。

ソニーの井出さんが内発的動機づけに関して紹介していた本。
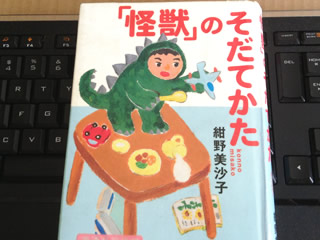
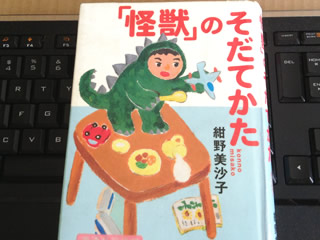 小さな子ども、特に男の子をもつ母親はみなさん思うんじゃないでしょうか、小さな子どもは「怪獣」だと。
小さな子ども、特に男の子をもつ母親はみなさん思うんじゃないでしょうか、小さな子どもは「怪獣」だと。
そんな怪獣を育てた女優の紺野美沙子さんが書かれた育児エッセイ本「怪獣のそだてかた」を読みました。

今年になって最寄り駅の近くに図書館ができて、本が借りやすくなりました。
ちょっと気なった本はインターネットで図書館のサイトからどんどん予約しています。タダで本が読めるなんてありがたい限りですが、タダゆえの難点もありますね。
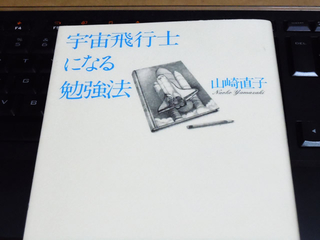
新聞広告で見かけて「宇宙飛行士になためにはどんな勉強をしたんだろう」とか「お子さんもいらっしゃるのに、子育てとどうやって両立したんだろう」という思って読んでみました。

具体的に宇宙飛行士になるための勉強法が載っているわけではありませんが、山崎さんの勉強法や生活の工夫など参考にしたい点が沢山ありました。

先日読んだ「子供の名前が危ない」という本が面白かった。
子供がいないので、最近の子供の名前を直接知ることはないのですが、ニュース等で見かける子供の名前など、たしかに読めない名前が多いです。先日もツイッターで「今鹿」という名前が話題になっていました。(読み方は最後に)
こうした読みにくい名前、キラキラネームとかOQN(ドキュン)ネームというそうです。

マーケティング戦略のについて、実際にどう考えどう行動したらいいか、物語にすることで読者に「体験」させる。

私にはあまり関係なさそうだけど、難しい相続の問題を分かりやすく説明してくれそうな本です。
磯野家といえばなかなか複雑な家族構成なので、いろいろと事例もありそうですねw。こちらは磯野家の家族構成は子供の頃か知ってるから、少々ややこしい関係でも理解できそうww。
わざわざ難しい本で勉強する気にはならないけど、こんな本なら気軽に読めそうだし、知っておいて損はない知識だし。
今度見つけたら読んでみる。

書店で児童向けのコーナーをのぞいてみたら、子供向けとあなどれない面白そうな本がたくさんありました。
その中の一冊が『こども武士道』
旧五千円札の肖像でもある新渡戸稲造が書いた『武士道』を子供にも分かりやすく紹介した本で、人として大切にしなければいけない心構えがわかりやすい文章とたのしいイラストで書かれています。
子供向けだからこそ余計な説明がシンプル。大人にもわかりやすいです。

『アイデアはどこからやってくる?』を読みました。
著者の岩井俊雄さんはメディアアーティストとして絵本、ゲーム、 TV番組など多方面で活躍しており、縦に開く絵本『100かいだてのいえ』や電子楽器『TENORIーON』、ジブリ美術館の『トトロぴょんぴょん』、テレビ番組では『ウゴウゴルーガ』などの製作に参加してます。
私が今でも好きな番組として挙げるのが『アインシュタインTV』で、また『時間層II』というアート作品非常に衝撃を受け、その両方が岩井さんのお仕事であることを知ってから、岩井さんのお仕事にずっと興味がありました。そして岩井さんの発想がどうやって生まれるのか、非常に興味深く読ませていただきました。
本書の中にはアイデアを生み出すためのポイントがたくさん紹介されています。
子供のころからの体験、工夫する・考える・気づく、常識にとらわれない広い視野をもつ、などすべて紹介したいところですが、とりあえず私が面白いったのは「不満を感じたときがチャンス」「常識となっていることの始め、歴史を知る」という点。これかの生活ではこれらの点に注意してみようと思いました。
この『アイデアはどこからやってくる?』は対象年齢が14歳以上ということで、平易な文章で読みやすく、また岩井さん自身の子育て経験もアイデアの元になってることから、パパママにも参考になる点がたくさんあり、幅広い層が楽しめる本です。

今、『ゲームの父 横井軍平伝』を読みはじめました。
まだ読み終わってませんが、以前読んだ『横井軍平ゲーム館』の内容を再構築した本だそうです。
まず、横井軍平について
このかたは、まだファミコンが登場する前、任天堂が花札やトランプの製造元として知られていたころに入社し、次々とヒット商品を開発していった人で、古くは『ウルトラハンド』『ウルトラマシン』『レーザークレー』などの玩具、そして『ゲームウォッチ『ゲームボーイ』の携帯電子ゲーム機まで、どれも当時大流行したものばかりです。
ここで注目したいのが「枯れた技術の水平思考」という考え方。
横井軍平はこれらの商品を最新の技術を使わず、むしろ使い古され安くなった技術を導入しています。たとえば、液晶画面は当時電卓のパネルにしか使われていなかったものをゲーム機に流用することで、安価に携帯ゲーム機を提供できたそうです。おかげでカシオは液晶パネルの受注が一気に3倍に伸びたとかw
この「枯れた技術の水平思考」は今でも任天堂に受け継がれ、WiiやDSの躍進の原動力になっているそうです。
ただしこの「枯れた技術の水平思考」とは、技術の応用方法ばかり考えているのではなく、もっとその先の目的があり、それを実現する手段として”必ずしも最新の技術が必要ではない、周りのあるもので十分可能かもしれない”ということです。
近年、この「枯れた技術の水平思考」について注目され、絶版となった『横井軍平ゲーム館』がネットオークションで90,000円以上の値がつくほどになり、あらためてこの『ゲームの父 横井軍平伝』が発刊となったそうです。
ゲームばかりではなく、柔軟な発想方法に興味のある方はぜひ読んでみてください。

職場の同僚から「とてもいい本だから」と薦められて、実は義理で読んでみたらホントに良かった。
両親に感謝しよう、他人の気持ちをよく考えよう、今の自分を認めよう、そう思える本です。
本の帯には”世界一わかりやすい、泣ける生命科学の本”という見出がありました。たしかに科学的な視点の話もありますが、感動するのは養護学校の先生と、難病を抱えて生まれてきた子供たちとその家族との交流についてです。
決して、その人たちと今の自分を比べて「自分は健康でよかった」というような感想ではなく、健康であるがゆえに普段気づかない何気ない幸せに気づかせてくれました。
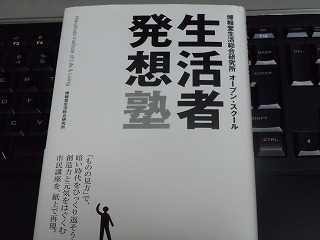
『生活者発想塾』という本を読みました。
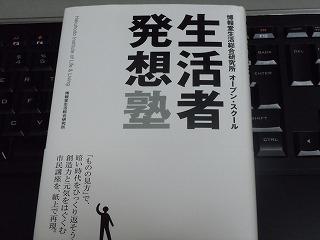
生活者発想塾とは、広告会社の博報堂が設立した研究所で2008年から実施しているオープンスクールで、その公開講座の内容を書籍にまとめたもので、生活者のニーズや未来を探るために、データの集め方や分析方法などが色々と紹介されています。
データや分析と言ってもそれほど難しい内容ではなく、ワークショップのように自分でもすぐに試せるような内容で、しかも複数でやるほど面白そう。
なかでも写真を使ったデータ収集が面白そうでした。簡単に内容を説明すると「あなたにとっての安心の素を撮影してください」「日頃の食卓の風景を朝昼晩と記録してください」「幸福を感じる物事を写真におさめてください」といったもの。
写真だと、アンケート(文字)やインタビュー(言葉)では伝えにくいことが伝えられたり、本人の興味や視点にいろいろと違いが出る。
ほかにもイメージとして使っている日常用語を数値に直して表現する「マインドスコア」、ある絵の中のセリフを考える「ダイアローグバルーン調査」なども興味深くて、実際のオープンスクールに参加してみたくなりました。
調べたら5月18日に開催されるようです。
http://www.nikkeibook.com/seminar/seikatsusha/

『体脂肪計タニタの社員食堂 500kcalのまんぷく定食』
株式会社タニタの社員食堂で提供しているヘルシーランチの定食レシピ31日分を掲載。
オーブントースターで油分カット、カロリーダウンの調理のコツ。かみ応えでまんぷく感、薬味で味わい、だしの工夫で塩分カットなど、おいしさそのままでボリューム感のあるヘルシーレシピ。
<目次>
・タニタ食堂へ、いらっしゃいませ
タニタ食堂って、どんな食堂?
タニタ社員の常識
実録!タニタ社員がほんとうにやせた! ほか
・本日の日替わり定食
521kcal─根菜とひき肉のしぐれ煮定食
479kcal─ささみのピカタ定食/
516kcal─さわらの梅蒸し定食 ほか
・ついでに作る大活躍の保存ソース
・裏メニュー
・食材使い回しさくいん
・食材分量目安一覧