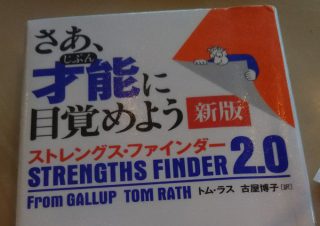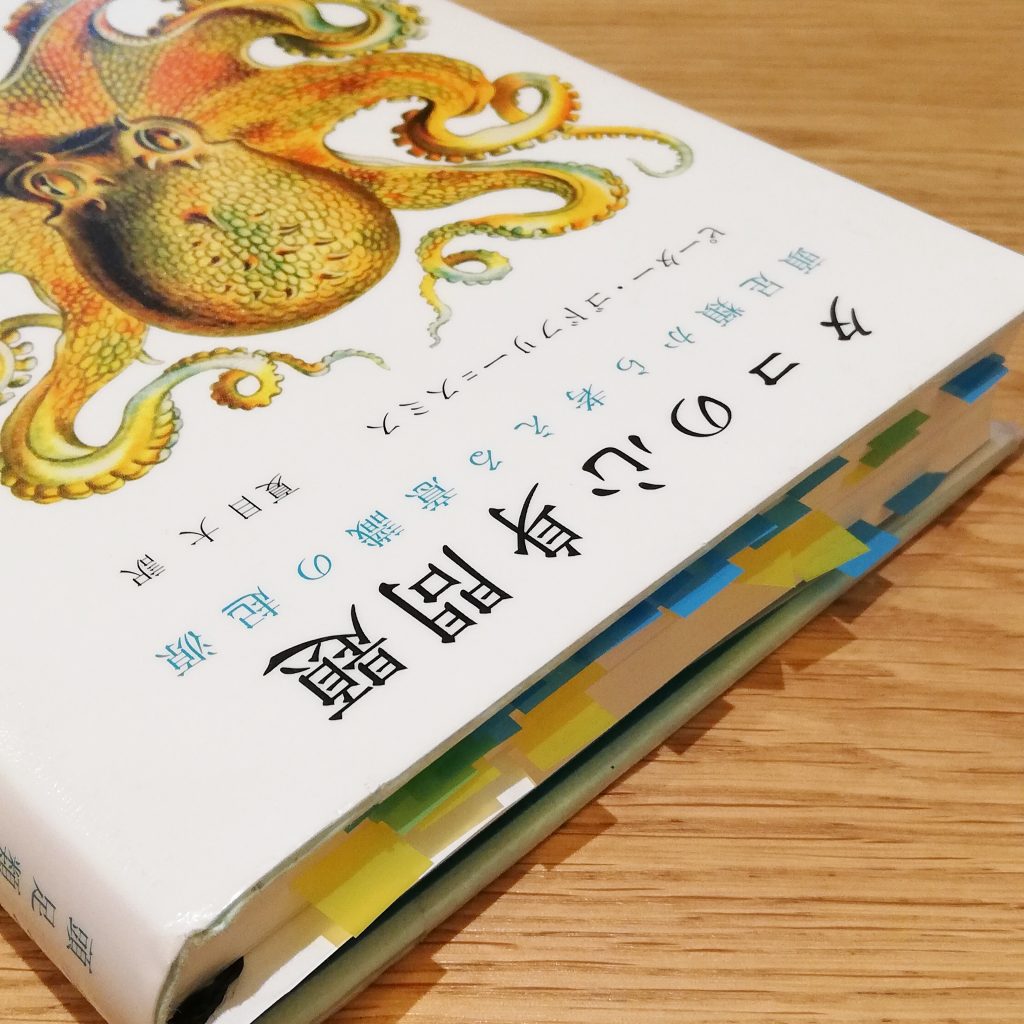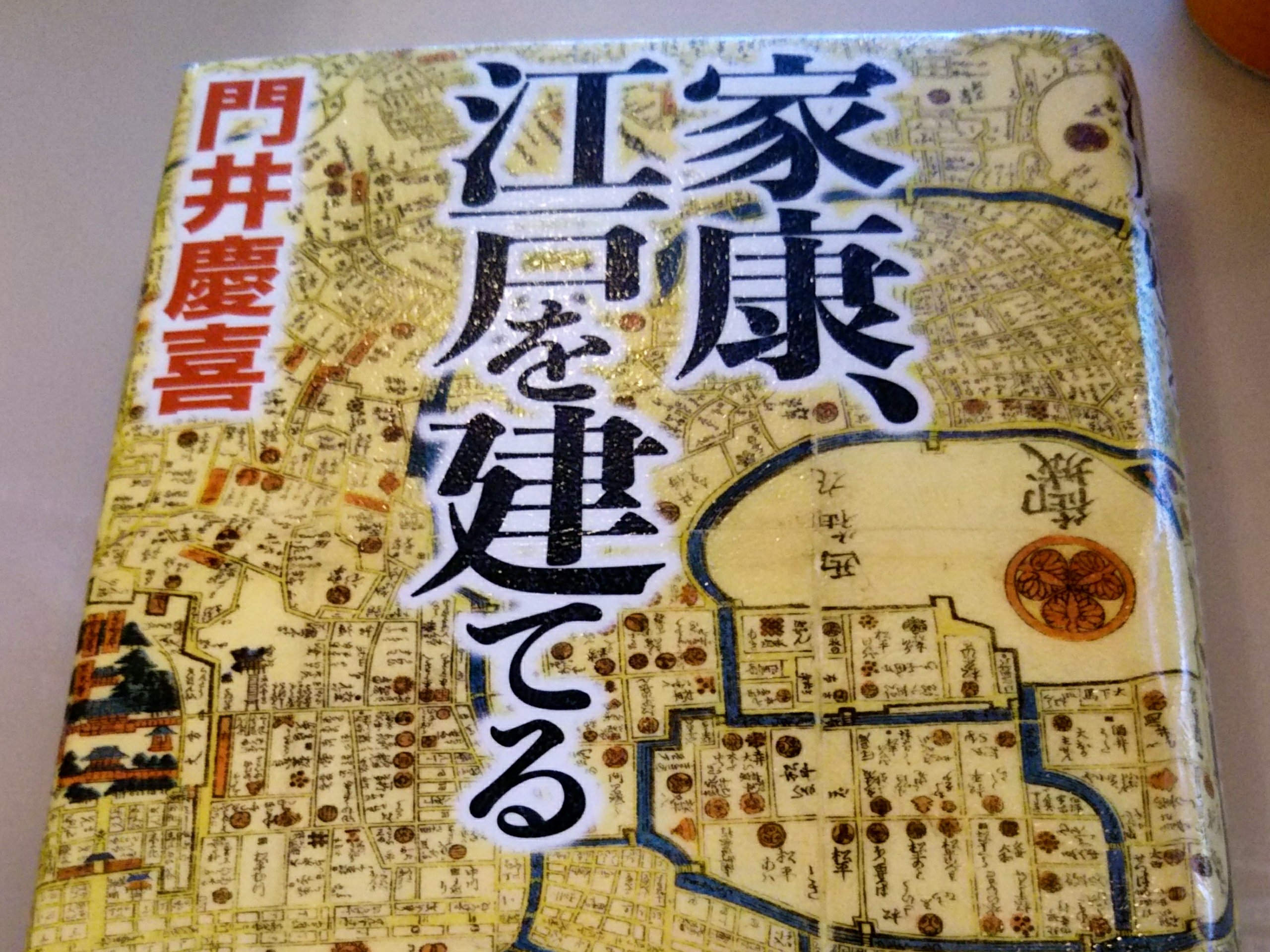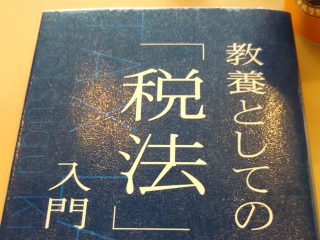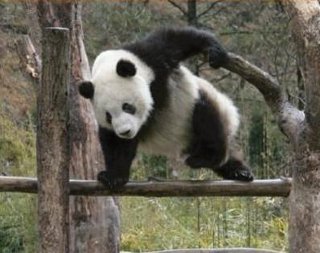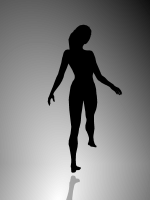へンな日本美術史
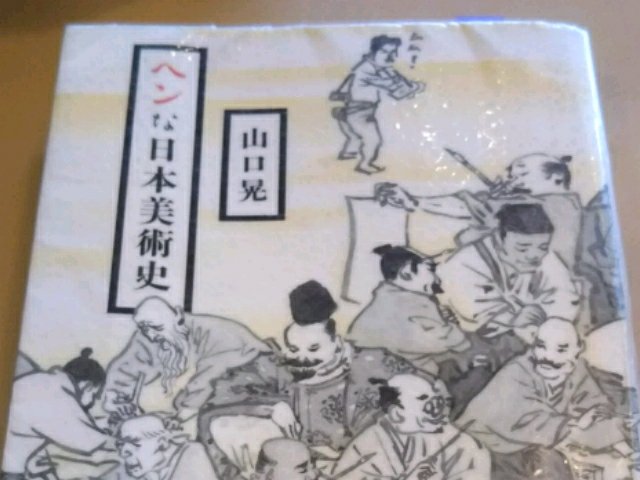
以前に読んだ『本気になって何が悪い』で紹介されていたことと、著者である山口晃さんの絵が好きなので読んでみた。
粒子の細かい墨、黒というより青み、透明度、色の奥行き
印刷では再現できない、材質と塗料
人間の目は常に動いており、画面から受ける光の角度も変化する
筆のクセがでるのは、力を抜いて描く部分。目鼻口は注意して描くが、耳などは力が抜ける。
日本画の特徴:仕上げすぎない。
白描画
・奥行きを表すような線などよりも、画面構成の心地よさを優先。
・詞書があることで、全く違う次元の空間があらわれる
・文字を絵に取り込み、さらに文字で絵を描いてしまう。
・現実を写すより、どこに何を置いたら良い感じか、感情が優先
・紙の地(白)がほのまま空間になる。後から塗れないという制限が逆に表現になる
・黒の使いかた:画面を引き締める物に置く(髪や烏帽子
一遍聖絵、絹にかかれた絵(絹本
・白をのせた瞬間に変化する
・絹に描くことの不自由さを活かす。画材の質を逆手に、白という色の特性を最大限に引き出す
・油絵の白も、白の置かれた層が、絵の層を見る手がかりになる
現実としてはあり得ないポーズでも、絵としては正解
子どもの絵は、塗りたい色で塗り、描きたい所に描く。ムダがない。考えだすとおかしくなる
絵としての完成度が高いのは、現実の部分とイメージの部分との中間を表したもの
歌舞伎の化粧が派手なのは舞台で映えるため。どこで見られるかという環境を考慮する必要がある。
絵が表装や額縁でどこにでも置けるようになった分、場所との関係が希薄になってしまった。
オリジナリティはどこから生まれるか:軸があれば、オリジナリティなどはそのゆらぎから生まれる
静止した動態:「外す」「崩す」ことにより中心からの距離がうまれ動きを含む
外すには中心がわかっていること
10の手間を全体にかけると完成度は5にしかならない。顔に8、残りを2にすると完成度が7、8と上がる
モンタージュより似顔絵のほうが犯人が見つかりやすい。
似顔絵は「こんな感じ」というだけで、相手の頭のなかで修正できる余地がある
日本の美術教育は中学まで。中途半端で終わってしまい、トラウマしか残らない。
(大人はどのように美術を学べばよいか
絵描きのウソは、観た人の心のなかに「本当」が焦点を結ぶよう、事実を調整した結果
上手い人の投げやりな絵より、下手でも一生懸命さは伝わる
対象の内面に迫るために
・西洋は細部まで忠実に描く
・日本は写実よりも「らしさ」を優先し、記号化された表現「型」にのせて鑑賞者に実を託す
写実でないところで実を捉える
売れるものは必然的に時代の空気を反映している
その時代を掘り下げて、人の世の基底部に届いていれば、現在性と普遍性が両立する
応挙の画論
・絵の確認は白日・昼の光で
・写生は実物よりも大きく見えてしまう。矯正法として鏡を見て描く、望遠鏡を見て描く
鏡:正像ではなく虚像の違和感があることで、観察が自覚的になる
望遠鏡:片目で見ることで、両目で見たときの立体視による形のゆらぎを取り除く
・面的に描いて輪郭線は控える
きちんと真似る
絵面をトレースするのではなく、絵の構造を真似る
筆運び、そのための体の動かしかた、描く順番、描く所、描かない所、対象を捉える観点などなど
見ながら描くと筆が止まる
一気に描く筆勢、筆跡を活かすには、頭のなかに焼き付け、記憶でかく。若冲は「神気」が見えてから描いた
日本なんぞに閉じこもってないで世界と勝負しろ
ゲルハルト リヒター
バルール(色
ヘンリー ダーガー 非現実の王国で
前賢故実